2020/04/24
2020/07/18
【独占】日本初「データサイエンス学部」創設の滋賀大・須江副学長インタビュー の一問一答

目次
―――日本初のデータサイエンス学部を創設した背景は?
須江氏:データは今や石油と比べられるぐらい21世紀の重要な資源だととらえられていて、プラットフォーマーが世界中のデータを集めて高度利用して付加価値を生み出すビジネスができていています。これらの企業群がそうやって大きな付加価値を手にしている一方で、日本国内では近年データ革命、データ駆動型社会への移行ということが叫ばれて、そういう意識も高まってきてはいますが、実際にそれをやろうとした時に、誰が担うのか、ということは大きな課題なのです。

技術的な進歩によって、コンピューターの利用やプログラミングに関しても、ある程度、簡単にできるようになってきていますが、問題は使い方で、テクノロジーを理解し、ビッグデータから価値を導き出すというプロセスを設定できる人たちが必要ですが、そのためのデータサイエンティストが国内で全然足りていませんでした。そこで、高等教育機関として初めて、本格的なプログラムを組んで教育を始めたというのが背景です。
―――データサイエンティスト育成の現状、米中と日本での差異は?
須江氏:日本の大学には、欧米はもとより中国・韓国などにも普通にある統計学部がなく、統計学を体系的に学ぶ機会・学生がほとんどありませんでした。データサイエンスの基盤となるのは情報学、統計学の2つ柱ですが、ICT(情報通信技術)の進展でビッグデータが出現してもなお統計科学を体系的に学ぶ専門学部がなく高等教育機関の大きな欠陥になっていました。
例えば、本学がデータサイエンス学部を作ろうとした2014~15年に米国には100ほどの統計学部があり、そして今や130以上まで増えています。それくらい、米国ではデータ人材の需要が引き続き高いということで、一部はデータサイエンス学部化も進みつつあります。
同じ時期に中国で200と言われた統計学部は、今では300を超えています。すさまじい勢いで統計科学を重視し、データを理解し分析できる人材をつくり出そうとしています。韓国にも統計学部があり、統計学博士を出しています。それに対して、日本では統計学部がゼロだったんです。滋賀大データサイエンス学部は、日本初の統計系の学部でもあるのです。
政府は第四次産業革命や「Society5.0」などを標榜したのは2016年ごろからなので、ビッグデータ時代の幕開けから10年以上経過していたわけです。
特に、専門人材を育成する学部がないということで、1990年代の米国の統計重視の教育改革から日本の人材育成は20年ぐらい遅れています。キャッチアップは大変でしょうが、きちんと教育を進めていけば、日本人もこの分野で十分能力を発揮できると思います。(米国を中心とする)プラットフォーマーが大きく先取りしている中で、これに勝つのはなかなか難しいですが、日本人の素養の問題ではないので、人材をきちんと沢山つくって、データを高度利用したビジネスの最適化や新しいビジネスを構築・展開していけば、日本の生きる道はまだまだあります。

出典:参考図1. IT 人材の需給に関する推計結果の概要 (経済産業省)
―――データサイエンスをめぐる産官学の共同研究・開発、企業との連携は?
須江氏:大学でデータサイエンスを教育する時に一番の課題は、現実社会のデータが大学にないということです。つまり、データは企業や自治体などにあるのです。滋賀大学は「データサイエンス学部」の2017年開設を決めたのですが、その1年前に「データサイエンス教育研究センター」をつくって、企業等との連携を進めていったのです。それは、実データに基づいた実践的な教育訓練をするためには不可欠の施策でした。
データサイエンス学部は統計系のデータアナリシス・情報系のデータエンジニアリングというスキルは理系的ですが実社会の課題を理解し価値創造を目指すという意味で文理融合型の複合領域にあります。理系の教育として、学生100人の講義は成り立つけれども、演習などは10~20人単位のグループをつくらなければならないので、それだけの教育者と資金が必要です。このため、企業からの寄付とか共同研究など、さまざまな形でかなりの外部資金が必要でした。つまり、企業連携を進めて、①実データを使えるようにすることを可能にし、②データサイエンスの実装面で共同研究等により企業を支援し、③寄付や研究費という資金を確保し、日本初の本格的なデータサエインス教育が全体としてできる体制を整えるという問題に対処したのです。
もう一つ、実践的な教育を進める上で重要な、学生がデータビジネスを理解できるようにするため、現場で活躍している若手のデータサイエンティストに講義してもらう機会をたくさんつくりました。現実社会のビジネスについては、大学の教員は必ずしも専門ではありません。そこで、新しい分野で活躍しているいろいろな業種の若手のデータサイエンティストに来ていただき、どのようなビジネスを展開しているのかを話をしてもらっています。それが学生にとって大きな刺激になっています。
こうした学生にとって難解な数学や統計学を学ぶためのモチベーションを高めてもらうことも重要です。さらにそのため、企業現場に直接足を運び、実習的な体験をする機会も提供していただいています。
しかし、データサイエンスの重要性について、日本企業の経営層はいわゆる文系出身の経営者が多く、その役割、可能性についての理解は、必ずしも十分とは言えません。企業側から『経営者に説明してほしい』という要望が多く本学に寄せられています。このため、企業経営の幹部に対して、データサイエンスの重要性や役割、データサイエンティストがどのようなことをできるのかというような話をして回っています。
その一方で意識の高い企業も多く、この分野で専門的に取り組む本学のような大学との連携やオープンイノベーションの重要性を理解していただき、学部設置からわずか3年ですがさまざまな業種との企業連携も加速しており、共同研究だけでも100以上の企業と行っています。
―――データサイエンス学部の卒業生の進路は?
須江氏:データサイエンスでは、理系のスキルを適用・実装し「社会での価値をどうやって生み出すか」ということが重要なので、どのように社会の課題を解決していくか、という意識を持つ学生が結構いるんですね。
マーケテイングや公的サービスを改善したいという人もいるでしょうし、製薬・創薬関係に進みたいと考える人たちもいるでしょう。鉄道あるいは自動車関係に進みたいとか、船(海運)をやりたいとか、どのビジネスでも先端的な分野では今や多量のデータを使ってビジネス構築や事業展開をしているので、進む分野はいくらでもあります。デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組むような企業であれば、どこでも就職対象になると思います。またいずれ自らビジネスを立ち上げる人たちも出てくることでしょう。
滋賀大学では日本初のデータサイエンス学部で上級生がいない状態で学部教育を始めているので、先輩の背中、ロールモデルを見せられない中で、できるだけはやく社会に溶け込む、社会経験をした方がいいということで、2年生の夏から、1カ月ぐらいの中期インターンシップに出しています。企業のデータ統括部門のようなところに置いてもらって、社内のデータ分析の依頼などに対応して分析して対応するというような体験をやっています。これは受入れ企業や派遣学生側双方から好評で、本学のデータサイエンス教育への評価にもつながっています。
企業から「結構できるじゃん」と評価をもらって、「卒業したらうちにおいで」と言われている学生も結構いるようです。金融機関にインターンシップに行ったある2年生は、営業用のツールを開発して、プロトタイプのプログラムをつくって置いてきたりもしています。

出典:滋賀大学
―――官、つまり政府内でデータサイエンティストのニーズは高い?
須江氏:EBPM(Evidence-based Policy Making、証拠に基づく政策立案)の必要性から人材ニーズは高いのですが、民間企業と比較して十分な報酬は中々出せないと思います。総務省統計局当時、今から数年前でも企業間では年収1500万円とか2000万円でデータサイエンティストの引き抜き合いをやっていたとも聞いています。今だと新卒の優秀な学生であれば、それぐらい出すという企業もあったりして、相当、競争が高い状態です。
今、政府は、総務省の統計研究研修所を政府内の官庁データサイエンティスト養成機関にするという方針を出しています。ただ、データサイエンティストが育つということは、民間に引き抜かれるということでもあるかと思うんです。しかし、僕はそれでもいいと思っています。
戦後まだコンピューターが普及していない時代に、当時の統計局はプログラマーを養成し、たくさん抱えていたので、結構、民間企業に引き抜かれたというようなことも聞いています。当然公共サービスの改善に取り組む人も沢山残るでしょうし、引き抜かれてもそれで社会全体が良くなるならいいと考えています。それにすくむより、引き抜かれるぐらいの高度なデータサイエンティストを育成できれば、評価されると思うんですよね(笑)
―――データサイエンスとAIは、日本社会とどのように融合していくべき?
須江氏:AI技術そのものは以前からありましたが、研究の進展とコンピューター性能とセンサーの向上などにより急速に実用化が進んでします。政府がAIと本格的に言い出したのは2016年ぐらいで、先般「AI戦略2019」を決定しました。画像処理とか、音声認識とか、大規模なデータを駆使して同定のフラグを立てられるので、効率化に貢献でき、すごく使いやすい面があります。
「データサイエンスをどうやって適用し使うか」「AIをツールとしてどう実装し使いこなしていくのか」ということが一番大事です。例えば入国管理などセキュリティー管理の様々な場面でAIによる画像判定が取り入れられていますが、多量の画像データをAIに処理させフラグを立てて、必要なところだけ人間がきちんとチェックすればいいということです。AIは多量のデータをリアルに処理できるので、(人間にとって)現実社会を運営していく上ですごく使い勝手の良いツールです。つまり、AIを使い効率化を図れるところにはどんどん普及してくと思います。
ただAI自身は、一つの答えを出すとか、最終判断をするにはちょっとふさわしくないというか、ブラックボックスのところが結構強いので、結果の理由や説明の面で難しい部分があります。その意味で、人間の判断をサポートするものとして、かなり浸透すると思います。
裁判の判例でも、企業会計の検査でも、AIがフラグを立てるという形で自動化をある程度進めていくという流れです。そういう流れが、いろいろな分野でもどんどん進んでくるので、人間が本当に判断しなければならないことだけを判断できるようにするための「粗ごなし」みたいなものを、AIに任せていくことになっていくことになるのだと思います。
一方で、AIは確率で計算しています、文脈を理解して判断しているわけではありません。その意味で、最終判断をさせるというのは結構しんどくて、AI自身の品質や信頼性をどう担保するか自体大きな課題なのです。AIはマーケテイングみたいな経済面では割合、使いやすいんです。しかし、制度とか、法律の適用とか、きちんとしているということを担保しなければいけないという分野では、なかなか進みにくいでしょう。
従って、例えば医療の現場では「AIに診断結果を告げられるよりも、お医者さんに言われる方が納得できる」という人間心理もありますので、(AIの活用方法を)うまく切り分けていくということが大切です。AIの全部が良い、悪い、というのではなくて、AIをどこまで使って効率化を図り、ここから先は人間がやった方がよい、というように、最適なすみ分けしていくということだと思います。世の中が進化を、(AIを活用し)人の手をかけなくてもうまく回るようにしていくということだと思います。

―――小中高校生へのメッセージを。
須江氏:若い人たちは、デジタル・ネイティブ世代で、小さい時からPCなどに触れ、その操作とともに、データを扱うとか、プログラミングをすることに慣れ親しんだ人たちがだんだん成長してくるという意味では、大分前に社会人になった人たちが学び直すよりは、はるかに親和性があります。物事をデータから見て、客観的に評価し世の中仕組みを変えたいと考える癖が付いてくるように、うまく育ってほしいな、と思います。
過去には、データを十分に使いきれずに「勘と経験」で決めていくということが多く、それはそれでエピソードとしては成果もあったし、悪いこともあったでしょう。恐らく、データ中心でやっても、個々の現象面ではいろいろなことがおきるでしょうけれど、確率的にははるかに改善するに決まっています。そうやって世の中は進化していくので、社会の最適化を進める上で、若い人たちの力はすごく大事です。
デジタル・ネイティブ世代のそういう若い人たちがデータサイエンスの分野で活躍するこれから社会では、AIなども当然使いこなしていくでしょうし、日本の未来は明るいし経済的にも十分稼げると思っています。
―――100年後のAIの位置づけは?
須江氏:あまり先の予想は難しいですが、人間が運転するよりも自動運転の方が、事故が起こりにくい時代に実際に入っているんです。そうは言っても、万が一があると言って、拒絶する人たちもいて、せめぎ合いが今、行われている状態です。
ただ、AI自体は高い品質と信頼性の担保をどうするかという面で常に難しい要素はらんでいます。それは、例えば入れるデータが変わると、違う判断になりうるということです。だから、データをコントロールされると、違うことをさせられる、ということになりかねません。
国家としては、そこを意識しながら運営するのだと思います。要するに、(AIを活用することで)便利にはなるけれども、完全自動化でお任せという社会は、物語としてはありますが、人間は疑うのだと思います。疑うというのは正当な感覚で、それがあれば歯止めが効き、おかしなことは長くは続かずに、改善できるのだと思います。そうやって(AIは人間との間で)軋轢を起こしながらも共存していく。良い社会になっていくのだと思います。
―――企業の経営トップなどにAI、データサイエンスの理解者を増やす必要性は?
須江氏:時代はデータという資源を如何に活用するかが利益の源泉になりつつあります。その意味で企業トップの指導力が問われています。必然的に理解できる人が残る社会にならざるを得ません。問題はそのスピードなのです。「何とかなるんじゃないの」という人ばかりがいつまでもいると、いつの間にか、利益が全部どこかに持っていかれるということが起こりかねませんね(笑)。

AVILEN・崔一鳴(写真左)と須江氏(写真右)

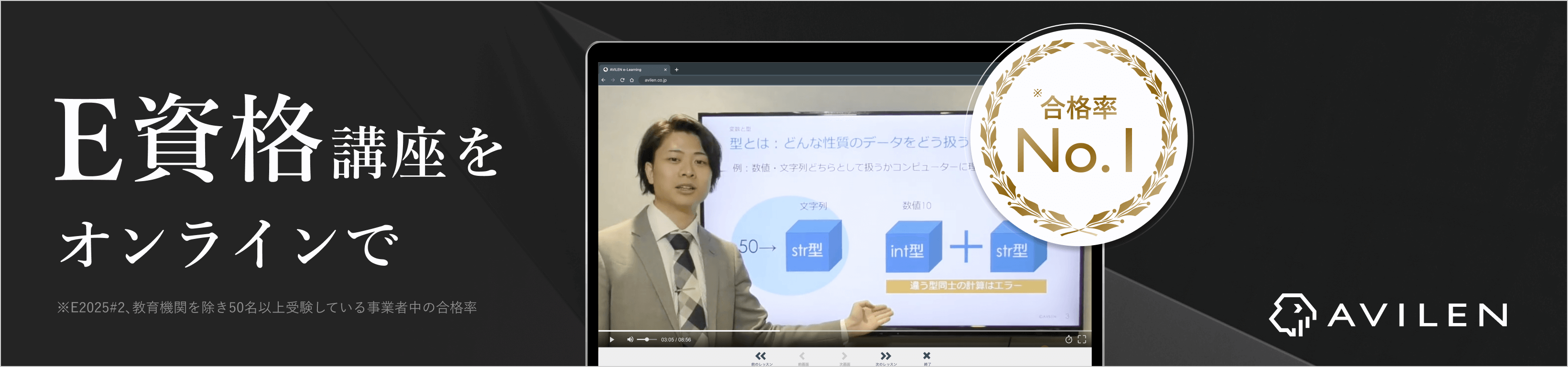







Recommended